損益分岐点をわかりやすく解説
2021年5月24日 最後に損益分岐点の計算シートを無料で用意しておりますので、ご活用ください。経営するうえで、必ず耳にする言葉だと思いますが、難しくて嫌煙しがちな内容だと思います。
そんな経営に必須である「損益分岐点」に関してわかりやすくアド博士が解説します
そもそも損益分岐点とは
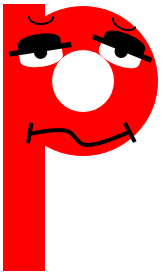
ペンタスくん
アド博士、損益分岐点ってこんな五字熟語言われても分かりませんよ
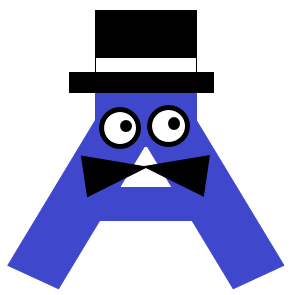
アド博士
ペンタスくん、難しい言葉は分解して考えたら分かりやすくなるんだよ。
今回の「損益分岐点」を分解して考えて見よう。
損益は「売上 – コスト(経費)」というシンプルな式で計算ができます。
入ってくるお金より出ていくお金が多ければ赤字、入ってくるお金が多ければ黒字と単純な事です。
しかし、損益分岐点は黒字でもなく赤字でもない、入ってくるお金と出ていくお金が等しくなる点のことを言います
そして、この損益分岐点が複雑な計算にするのが、コストの特性からです。
コストには固定費と変動費と大きく2つに分かれ、この2つに分かれるが故に、「損益分岐点」という複雑な計算をしなければいけなくなります。
コスト
コストは出ていくお金、すなわち支出のことを言い、大きく分けて「固定費」と「変動費」に分ける事ができます。しかし、この2つに関してもある項目の一部は「固定費」として計上し、一部は「変動費」として計上するように単純に仕分けできないのも複雑な要因のひとつとなります。
固定費
家賃・社員人件費・水道光熱費(基本料金)・リース料・広告宣伝費固定費は売上や集客などには関係なく発生するコストです。
変動費
水光熱費(使用料金)・人件費(アルバイトスタッフ分)・仕入れ原価(食材・ドリンク)・消耗品・その他(雑費等)変動費は売上に応じて変動するコストです。
高稼働になれば必然とスタッフの労働時間は増え(人件費が増加)低稼働であれば人件費は下がります。
また高稼働ということは、注文が多い訳ですので、仕入原価なども変動します。
なぜ損益分岐点が必要なのか
.jpg)
固定費+変動費=コスト合計
コスト合計を上回る点を「損益分岐点」と言います。
このグラフを見るだけであればシンプルに「損益分岐点=売上-固定費-変動費」となりそうですが、この式では残った売上要するに「利益」を求める式になります。
損益分岐点は「売上=固定費+変動費」となる点、ようするに利益も損失も出ない点のことを「損益分岐点」と言います。
こんなことを思うと思います。損益分岐点って必要?(現に私が店長をしている時は、利益だけで良いじゃん、って思っていました)
この損益分岐点は経営する以上絶対に必要で、その理由としては「売上目標」を設定するために必要だからです。
もし、損益分岐点を下回る売上目標を設定すると一生赤字です。
反対に損益分岐点を大きく上回る様な売上目標を設定すると何か支障が出てきます(例えば、高すぎて達成できない。無理に売上を取りに行くために無茶な営業をしてしまう等…)
もっと分かりやすく必要性を説くと
1個の商品の販売額を設定するために必要な訳です。
1個の商品を作るために以下の様なコストがかかります
・仕入原価・・・・・50円
・作る人件費・・・・作成に5分=人件費80円
・作る水光熱費・・・ガス・水道で10円
・諸経費・・・・・・100円
この合計は240円です。
この240円がいわば「損益分岐点」です。
300円で販売すれば60円の利益が出ます。
200円で販売すれば40円の損失を生み続けます。
損益が出る点を理解することで、販売額や割引キャンペーンなど多くの数字に反映させる事ができる訳です。
計算方法
こんなことを言うと元も子もないですが、以下の式が損益分岐点を求める式です。丸暗記してください。
固定費 ÷ {(売上 – 変動費) ÷ 売上 }
この式の解説をすると一つの記事が出来上がるぐらい多くの計算要素を簡素化した式になります。
またこの計算式に関しては解説したいと思います
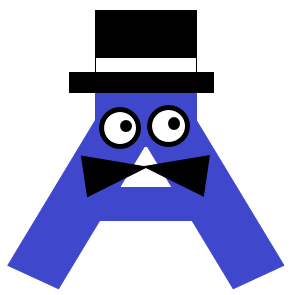
アド博士
いかかだったかな?
分かったような分かってないような感じではないか?
頭で理解できても、気持ちで理解できてないからじゃの。
実際にやって見て、自分の目で見ないと人間は飲み込めないからの。
下に計算用のシートを無料で用意しておるから使ってみるんじゃの!
コピーしてご利用ください
過去の実績を入力すると将来の数字も予測されますので、経営・営業にご活用ください。
.jpg)



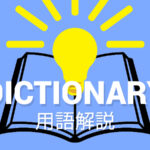


コメント